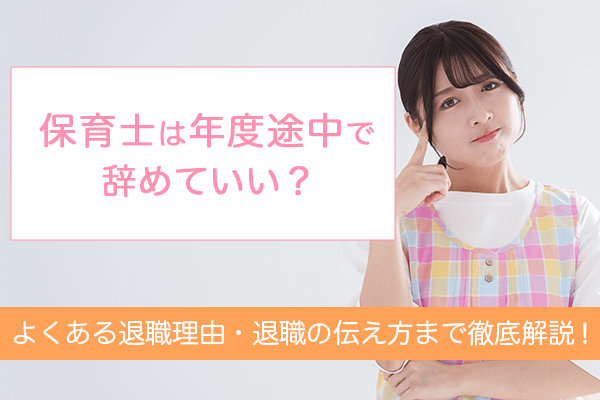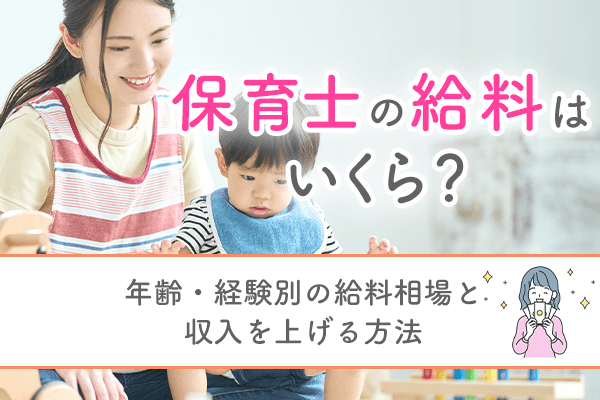新卒・若手・ベテランを問わず、年度途中で「もう辞めたい」と感じる保育士は決して少なくありません。
保育士という仕事は、精神的にも肉体的にも大きな負担がかかります。
無理をして続けることで体調を崩してしまえば、その後のキャリアにも影響しかねません。
ただし、年度途中で辞める場合は周りへの迷惑が掛からないように配慮しましょう。
また、年度途中で転職先に入園できる保証はないため、計画的に進めて行くことが大切です。
本記事では、年度途中での退職にまつわる不安を解消し、悩みを整理するための情報を詳しく解説しています。

保育士は年度途中で本当に辞められるの?
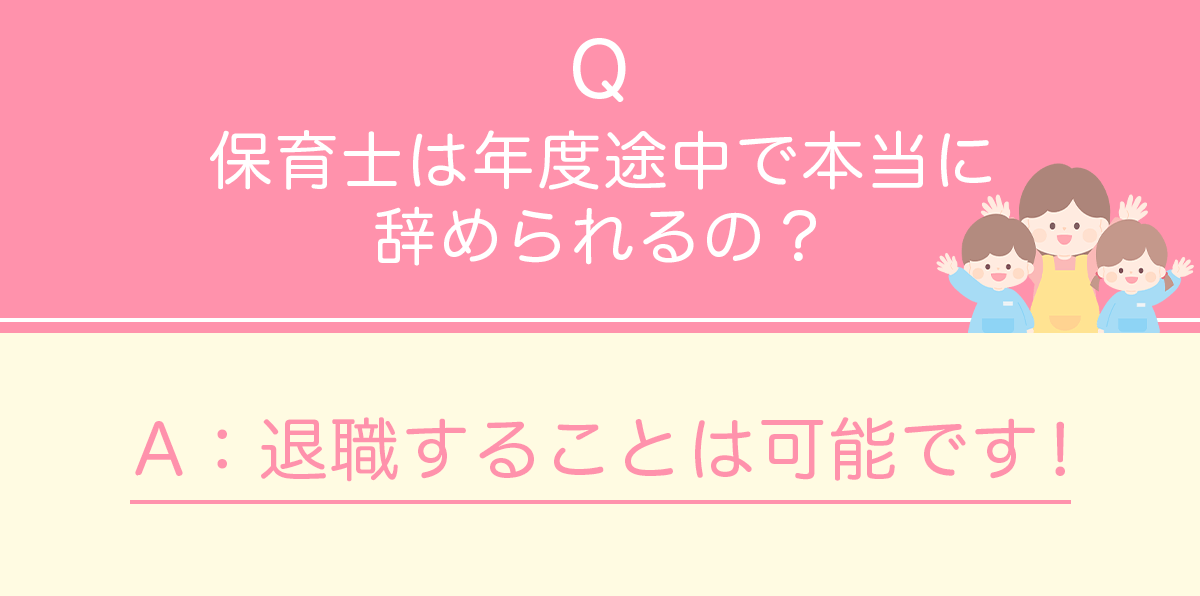
民法では「2週間前に意思を伝えれば退職できる」と定められており、就業期間の途中であっても辞めること自体は可能です。
ただし、現場では就業規則や人員体制の都合が関わるため、法律どおりに動くのが難しいケースもあります。
特に担任を持っている場合、急な退職は子どもや保護者への影響が大きくなります。
辞める自由があるとはいえ、円満な退職のためにはタイミングや伝え方に一定の配慮が必要です。
保育士が年度途中で辞めたくなる理由とは?よくある退職理由を紹介
保育士が年度途中に退職を考える背景には、以下のような事情があります。
- 人間関係のストレスが限界
- 給料が低く割りに合わないと感じる
- 業務量・責任がキャパオーバーしている
- うつ・不眠など体調不良や精神的な不調がある
- 妊娠・引越し・家族の事情などによるやむを得ない退職
特に日々の業務量や人間関係、体調不良、生活環境の変化などは、多くの人が共通して悩むポイントです。
厚生労働省の「保育士の現状と主な取組」の退職した理由から、職場の人間関係が33.5%と最も多くなっています。
次いで、「給料が安い(29.2%)」「仕事量が多い(27.7%)」「労働時間が長い(24.9%)」とった、職場環境に関する悩みが上位を占めています。
その後は、「妊娠・出産(22.3%)」「体力を含む健康上の理由(20.6%)」を理由に辞める方が多いようでした。
ここでは、保育士が年度途中で退職する主な5つの理由をピックアップし、詳しく解説します。
人間関係のストレスが限界
保育現場における人間関係のトラブルは、年度途中の退職理由として多く挙げられています。
先輩や同僚とのコミュニケーションが取りにくい職場では、報告・相談・連携がうまくいかず、孤立感を覚えることも。
また、無視や厳しい言葉が日常的に飛び交う環境では、精神的な負担が蓄積されやすくなります。
保育士はチームで働く職業だからこそ、人間関係の悪化は業務全体に大きな影響を及ぼす要因となるのです。
保育士の人間関係で悩む方に向けた解決策などはこちらで紹介しています!
給料が低く割りに合わないと感じる
保育士の待遇に関しては、長年課題とされている「給与の低さ」に対して不満を抱える人が多く見られます。
業務の幅が広く、体力的・精神的な負担も大きい中で、月収20万円前後という水準に対し「見合っていない」と感じる声が多いのが現状です。
賞与が少ない、残業代が出ないといった待遇も、離職の引き金になる要因となります。
生活にゆとりが持てない働き方が続けば、やりがいよりも不安が上回り、退職を検討することは避けられない流れとなります。
保育士の給料事情について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください!
業務量・責任がキャパオーバーしている
保育士の仕事は、子どもの対応だけでなく書類作成や行事準備、保護者対応など幅広い業務が求められます。
特に担任を任されると責任が重くなり、毎日の業務に追われる状態が常態化することもあります。
休憩時間が取れない、持ち帰りの作業が続くといった状況が続けば、身体的・精神的にも限界を感じるのは当然です。
十分なサポート体制が整っていない職場では、キャパシティを超えて働く保育士が多く見られます。
うつ・不眠など体調不良や精神的な不調がある
長時間労働や過度なプレッシャーが続くことで、体調不良を引き起こす保育士も少なくありません。
頭痛や胃痛、不眠、食欲不振といった身体的な不調に加え、気分の落ち込みや無気力など精神的な不調に悩まされるケースもあります。
特に朝起きられない、涙が止まらないといった症状が現れている場合は、早めの対応が必要です。
年度途中であっても、健康状態が優れない場合は、退職を視野に入れることが大切です。
妊娠・引越し・家族の事情などによるやむを得ない退職
結婚や妊娠、出産、家族の転勤、介護などライフイベントによって、保育士としての働き方を見直さざるを得ない状況もあります。
これらの事情は本人の努力で解決できる問題ではないため、退職という選択をすることも必要な対応です。
ライフステージの変化に応じて、無理のない働き方に切り替える判断は、キャリアを長く続ける上でも有効な方法といえます。
勤務先と相談しながら、できるだけ円満な形での退職を目指すことが求められます。
保育士が年度途中で辞めたいと迷っているときの判断軸
「このまま続けるべきか、それとも辞めたほうがいいのか」。
年度途中の退職を考えたとき、多くの保育士がこの葛藤を抱えます。
すぐに答えを出すのが難しいときは、いくつかの視点から冷静に整理することが大切です。
ここでは、自分の状況を見つめ直すための判断軸をご紹介します。
- 辞めることで得られる安心とリスクのバランスを見る
- 改善の可能性があるか冷静に見極める
- 自分の「限界ライン」を明確にする
辞めることで得られる安心とリスクのバランスを見る
退職すれば、今感じているストレスからは解放される可能性があります。
一方で、次の職場探しや収入面の不安が生じることもあるでしょう。
大切なのは、現在の職場にとどまることで失うものと、辞めることで得られる安心のどちらが大きいかを冷静に見極めることです。
「辞めると生活がどうなるのか」「心身の安定は取り戻せるのか」など、自分にとってのリスクとメリットを具体的に書き出してみると、判断しやすくなります。
改善の可能性があるか冷静に見極める
人間関係や業務の負担など、今感じている悩みが今後も変わらないのか、それとも改善の余地があるのかを考えることも重要です。
例えば、園長や主任に相談すれば業務量が調整できる可能性があるか、異動や配置換えの希望が出せるかなど、選択肢を探ることで状況が変わるケースもあります。
感情だけでなく、園の体制や対応の可能性を含めて考えることで、後悔のない選択につながります。
自分の「限界ライン」を明確にする
「あとどのくらいなら頑張れるか」という視点ではなく、「これ以上続けると心や体に影響が出る」と感じるラインを明確にすることが大切です。
睡眠不足が続いている、不安や緊張で体調を崩している、気持ちが不安定になっているなど、心身の不調が現れているなら、それはひとつの限界のサインです。
退職する・しないの判断において、自分の健康と尊厳を守ることを第一に据えることが必要です。
保育士が年度途中で辞めるデメリットと注意点
年度途中での退職には、メリットもある一方で、見過ごせないデメリットや注意点も存在します。
感情のままに辞めてしまうと、後から「もっと考えておけばよかった」と後悔する可能性もあります。
退職にあたって押さえておくべきリスクと注意点を整理しておきましょう。
- 引継ぎや保護者対応が不十分だとトラブルのもとに
- 希望の転職先を見つけられない可能性が高い
- 次の職場での印象に影響することもある
引継ぎや保護者対応が不十分だとトラブルのもとに
急な退職では、業務の引継ぎや保護者への説明が不十分になりがちです。
特に担任を持っていた場合、園児の情報や保育方針の共有が曖昧なままになると、後任の保育士が戸惑い、保護者からの不信感につながる可能性があります。
退職後にトラブルが起きてしまうと、自分の評価や信頼にも影響を及ぼす恐れがあります。
円満に職場を去るためには、できる限りの情報をまとめ、誠意ある対応を意識することが大切です。
希望の転職先を見つけられない可能性が高い
年度途中に転職活動を行う場合、求人の数が限られていることがあります。
特に希望条件が多い場合や、地域が限定されている場合には、選択肢が少なくなりがちです。
また、転職先の面接で「なぜ年度途中で辞めたのか」を問われた際に、明確な理由がなければ印象を悪くしてしまうことも考えられます。
転職市場のタイミングや、自分が希望する条件に合う職場がすぐに見つかるとは限らない点には注意が必要です。
次の職場での印象に影響することもある
前職を短期間で辞めた経歴は、次の職場での評価にも影響を及ぼす可能性があります。
採用側から見ると「またすぐ辞めてしまうのでは?」と不安視されることもあり、書類選考や面接で不利になるケースも少なくありません。
ただし、退職理由が明確であり、納得感のある伝え方ができれば問題視されないことも多いため、経歴だけでなく伝え方の準備も重要です。
いずれにしても、転職先にどう見られるかという視点を持ちながら退職時期や理由を整理しておくことが求められます。
保育士が年度途中で辞める旨は3ヵ月前までに伝える
年度途中で退職する場合は、法律上は2週間前の申し出で退職は可能とされていますが、担任の引継ぎや人員補充に時間がかかるため、3ヵ月前を目安に伝えるのが望ましいとされています。
保育園側も年度途中での人材確保は難しく、急な退職は現場に混乱を招く原因となります。
そのため、なるべく早い段階で退職の意思を上司に伝えることで、円滑な引継ぎや保護者への説明にも余裕が持てます。
特に担任を持っている場合や、行事・クラス運営に深く関わっている場合は、他の職員にも大きな影響を及ぼすことになるため、事前の計画と配慮が大切です。
【例文】保育士が年度途中で辞める理由の伝え方
年度途中で退職する場合、「どう伝えるか」に不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
退職理由は、勤務先や保護者、転職先など、相手に応じた伝え方が必要です。
曖昧すぎても不信感を与えますし、ネガティブな印象が強すぎてもトラブルにつながる可能性があります。
ここでは、それぞれの相手別に伝え方のポイントと例文をご紹介します。
- 勤務中の保育園への退職理由の伝え方は感情的にならず丁寧な言葉を選ぶ
- 転職先の保育園への退職理由の伝え方は前向きな姿勢で伝える
- 保護者への退職理由の伝え方は不安や混乱を与えないようにする
勤務中の保育園への退職理由の伝え方は感情的にならず丁寧な言葉を選ぶ
職場に対して退職を伝えるときは、正直な理由を伝えつつも、感情的にならず丁寧な言葉を選ぶことが大切です。
「職場に不満があるから辞める」というような表現は避け、あくまで個人の事情として伝える方が受け入れてもらいやすくなります。
私事で恐縮ですが、体調面の不安が続いており、今後の業務に支障をきたす可能性があるため、退職を検討しております。
園には大変お世話になり、感謝しておりますが、心身の安定を優先し、円満に引継ぎを行ったうえで退職させていただければと考えています。
転職先の保育園への退職理由の伝え方は前向きな姿勢で伝える
新しい職場での面接では、「なぜ前職を辞めたのか」がほぼ確実に問われます。
ネガティブな事実があっても、前向きな姿勢で伝えることが印象を大きく左右します。
自分の価値観や希望と合わなかったという伝え方にするのが効果的です。
現職では多くのことを学ばせていただきましたが、自分の保育観と業務の進め方にギャップを感じることが増えました。
より子ども一人ひとりに寄り添える環境で働きたいと考え、転職を決意しました。
保護者への退職理由の伝え方は不安や混乱を与えないようにする
保護者に対しては、業務上のトラブルや内部事情を詳しく伝える必要はありません。
あくまで個人的な理由であることを簡潔に伝え、不安や混乱を与えないように心がけましょう。
また、最後まで責任をもって対応する姿勢を見せることが信頼につながります。
私事ではございますが、一身上の都合により〇月をもって退職させていただくことになりました。
これまで温かく見守ってくださり、心より感謝しております。
残りの期間も、子どもたちと楽しい時間を過ごせるよう、精一杯努めてまいります。
体調不良・うつ症状で辞めるときは診断書を用意しておく
体調不良や精神的な不調が理由で退職する場合、医師からの診断書を準備しておきましょう。
自己申告だけでは職場が納得しづらいケースもあり、特に年度途中の退職では周囲の理解を得にくい場面が出てくることもあります。
診断書があることで、体調面の問題が客観的に証明され、無理な引き止めやトラブルを防ぎやすくなります。
また、退職後に失業保険を受け取る際にも、体調不良を理由に「特定理由離職者」として扱われる可能性があり、給付開始時期が早まるなどのメリットを受けられることもあります。
うつ症状や不眠、過度なストレスによる体調不良がある場合には、無理に我慢せず、心療内科やメンタルクリニックなどの専門機関を早めに受診するようにしましょう。
保育士が年度途中で辞めるまでにやるべき準備と引継ぎ内容を解説
年度途中で退職する際には、退職を伝えるタイミングだけでなく、引継ぎの準備が大切です。
自分が担っていた業務をスムーズに後任へ渡せるようにしておくことは、円満退職の基本であり、周囲への最低限の配慮でもあります。
特に担任を受け持っている場合は、園児の健康情報や性格、保護者との関係性など、細やかな情報の共有が欠かせません。
業務の抜けや漏れがあると、子どもたちや保護者に不安を与える原因にもなるため、以下のようなポイントを押さえておくと安心です。
- 園児・保護者情報は健康や性格、対応方法などを記載する
- 日々の業務や書類・行事の進行状況まとめておく
園児・保護者情報は健康や性格、対応方法などを記載する
引継ぎをスムーズに行うためには、園児一人ひとりの基本情報と関わり方を簡潔に整理しておくことが重要です。
以下のような表を用意して記録しておくと、後任保育士が即座に内容を把握しやすくなります。
| 項目 | 記載内容の例 |
|---|---|
| 氏名(ふりがな) | 転職 花子(てんしょく はなこ) |
| 生年月日・年齢 | 2020年2月10日生(4歳) |
| 健康情報 | アレルギー:卵/持病なし |
| 性格・特徴 | 初対面に緊張しやすい/絵本が好き/集中力あり |
| 配慮点・注意事項 | 集団行動が苦手/怒られると黙り込む傾向あり |
| 家庭事情・保護者対応 | 父親が単身赴任/母親が送り迎え/園への要望あり(連絡帳頻度) |
※個人情報の取り扱いには十分注意し、職員間でのみ共有するようにしてください。
このような表を1人ずつまとめておくことで、園児の特性や保護者との関係性を短時間で把握できるようになります。
フォーマットはExcelやGoogleスプレッドシートなどで作成すると、他の職員とも共有しやすくなります。
日々の業務や書類・行事の進行状況まとめておく
業務の全体像や進行中のタスクは、一覧にして渡せるようにしておきましょう。
事前にまとめておくことで後任も混乱せずに業務をすることができます。
主にまとめておくことは以下の通りです。
- 1日の保育スケジュール(時間ごとの活動内容)
- 行事の準備状況と役割分担
- 書類や記録の提出期限・フォーマット
- チーム内での連携ルールや日常的な流れ
とくに、保育園独自のやり方やローカルルールがある場合は、それを明記しておくことで引継ぎ後のミスや混乱を防ぐことができます。
保育園を辞めるときは必要書類を保育園から受け取る
退職後の手続きをスムーズに進めるためには、保育園から受け取るべき必要書類を事前に確認しておくことが大切です。
- 雇用保険被保険者証
- 離職票
- 年金手帳
- 源泉徴収票
退職の手続きが完了してから数日〜2週間ほどで届くことが一般的です。
これらの書類が手元にないと、失業保険の申請や年末調整、次の職場での手続きに支障が出る可能性があります。
退職が決まった段階で、早めに担当者へ依頼・確認しておくと安心です。
雇用保険被保険者証
雇用保険保険者証は、雇用保険に加入していた証明書で、主に失業給付や就職支援制度の利用時に必要となります。
この書類は企業が保管しているケースが多いため、退職時に返却してもらえるよう確認しましょう。
退職後にハローワークへ求職申請を行う場合には、必ず提示が求められます。
もし紛失していた場合でも、ハローワークで再発行が可能です。
離職票
離職票は、退職後に失業手当を受給するために必要な重要書類です。
「離職票-1」「離職票-2」の2種類があり、退職した本人の申請によって発行されます。
- 離職票-1:ハローワークが作成する書類で、失業給付が支給される際の退職者情報が印字されている。
- 離職票-2:複写式の離職証明書のうちの1枚で、退職理由や賃金について記載されている書類。
保育園側に「離職票の発行を希望します」と伝えておかないと、自動的には発行されないこともあります。
書類の発行・発送までには数日〜2週間程度かかる場合があるため、退職日が近づいたら早めに申請しておきましょう。
参考:ハローワークインターネットサービス│雇用保険の具体的な手続き
年金手帳
年金手帳は、厚生年金や国民年金の加入記録が記載された手帳です。
すでにマイナンバーによる管理に移行されているものの、次の職場での提出を求められる場合や、自分の記録を確認する際に使用することがあります。
職場が預かっていた場合には必ず返却してもらい、手元に保管しておきましょう。
紛失している場合は、年金事務所で再発行が可能です。
源泉徴収票
源泉徴収票は、その年の所得と支払った所得税額が記載された書類で、年末調整や確定申告に必須の資料です。
次の職場に提出することで、年末調整が正しく行われ、税金の過不足が調整されます。
退職後に郵送される場合も多いため、送り先を確認し、いつ発行されるのかの目安も事前に尋ねておくと安心です。
受け取りが遅れると、確定申告の時期に慌てる原因になります。
保育園を辞めるときは支給物の返却をする
保育園を退職する際には、園から支給された物品や備品を忘れずに返却しましょう。
- 健康保険証
- 入園証や名札、合鍵
- 通勤定期券
- 備品
返却漏れがあると、園側で管理に手間がかかったり、後から連絡が来て再対応が必要になることもあります。
スムーズな退職と信頼関係の維持のためにも、支給物のリストをあらかじめ確認し、整理しておきましょう。
健康保険証
社会保険に加入していた場合は、保育園から支給された健康保険証の返却が必要です。
退職日をもって保険の資格が失効するため、使用できなくなった保険証は必ず封筒などに入れて返却しましょう。
なお、退職後は国民健康保険への切り替えなどの手続きが必要になるため、役所での対応も忘れずに行ってください。
入園証や名札、合鍵
子どもとの関わりに使う名札やセキュリティ管理に関わる合鍵などは、保育園の所有物になるため返却しましょう。
これらは園の備品であると同時に、セキュリティ上の管理物でもあるため、退職前に必ず返却してください。
紛失している場合は、必ず上司や担当者に報告して対応を相談するようにしましょう。
通勤定期券
通勤手段として定期券代を園から支給されていた場合、その定期券も返却対象になります。
交通系ICカードの私物使用など例外もありますが、園で一括管理していた場合には返却が必要です。
また、残額がある場合は返金の対応が求められることもあるため、詳細は事務担当に確認しておくと安心です。
備品
教材、ノート、事務用品、園内で使っていたタブレットや貸与物など、園から支給されていた備品も返却しましょう。
使用頻度が高くなるうちに自分の持ち物と混在しているケースもあるため、「何を借りていたか」をリスト化して確認することが大切です。
特に電子機器や園の備品に該当する物については、返却後に初期化や点検が必要な場合もあります。
保育士が年度途中に辞めたいなら保育士求人JOBSに相談

年度途中での退職は決して珍しいことではありませんが、「次の職場が見つかるか不安」「保育士を続けるべきか迷っている」など、不安が多いのも事実です。
そんなときは、保育士専門の転職支援サービス「保育士求人JOBS」にご相談ください。
現場を経験した元保育士のキャリアデザイナーが、あなたの悩みや状況に寄り添い、無理のない働き方をご提案します。
「転職するか決まっていないけど、話だけ聞いてみたい」そんな方も歓迎です。
LINE相談・電話・メールなど、相談しやすい方法でご利用いただけます。
\まずは話してみるだけでもOK/

保育士が年度途中で辞めるときのよくある質問
保育士が年度途中で辞めるときのよくある質問を紹介します。
年度途中で辞めたいけど迷惑と言われるのが不安
年度途中の退職に罪悪感を抱える方は多いですが、自身の健康や生活を守る選択は「迷惑」とは別問題です。
もちろん急な退職は配慮が必要ですが、正当な理由があれば退職する権利があります。
大切なのは、引継ぎや周囲への説明を丁寧に行うこと。
誠意をもって対応すれば、周囲の理解も得やすくなります。
保育士が年度途中に転職に不利になるって本当?
転職時に不利になるかどうかは、「なぜ辞めたのか」をどう説明できるかにかかっています。
たとえ短期間での退職でも、体調や人間関係、価値観の不一致など、合理的な理由があれば問題にされないケースも多いです。
面接では前向きな理由に言い換えて説明できるよう、事前に整理しておきましょう。
年度途中で辞める人は多いのか?
実際には年度途中で辞める保育士は少なくありません。
厚生労働省の調査や保育士養成校のデータでも、1年未満の離職は一定数存在しています。
理想と現実のギャップや人間関係の悩み、体調不良などで早期退職に至るケースも多いため、「自分だけが弱い」と感じる必要はありません。
保育士が年度途中で辞めることに関するまとめ
保育士が年度途中で退職することは、問題ありません。
人間関係の悩み、業務負担、心身の不調、ライフスタイルの変化など、背景にはさまざまな事情があります。
「年度途中だから辞めてはいけない」と思い込まずに、まずは自分の状態と向き合い、最善の選択を考えることが大切です。
退職にはデメリットや注意点もありますが、事前準備や誠実な対応をすれば、円満に辞めることは十分可能です。
また、辞めたあとの不安を減らすためには、書類や引継ぎ、今後の働き方についての情報整理も欠かせません。
もし、「もう限界かもしれない」「辞めたいけれど、どう動けばいいかわからない」と感じているなら、一人で悩まず、保育士求人JOBSに相談してください。
専門家の視点から、新たな選択肢が見えてくることもあります。
あなたが無理をせず、安心して働ける職場を見つけましょう。