「保育士に向いてない人の特徴ってあるの?」
「保育士に向いてないから辞めたい」
保育士として働いていると、「私、保育士に向いてないのかな…?」と感じたことがある方も多いのではないでしょうか。
特に新人保育士や実習生は、初めての環境や仕事の難しさに直面し、自信を失ってしまうこともあります。
- 保護者とのコミュニケーションが苦手
- 職場環境と人間関係が合っていない
- 業務量が多く体力や健康面が続かない
- 子どもとのコミュニケーションが上手くできない
- 子どもに対して愛情が薄れてきている
しかし、その悩みは決して悪いことではなく、自分を見つめ直し、成長するきっかけになるかもしれません。
本記事では、「保育士に向いてない」と感じる理由や特徴、そして前向きに乗り越えるための対処法を詳しく解説していきます。
保育士の今後について相談、転職を考えている方におすすめの求人サイトも紹介しているためぜひ参考にしてください。
\保育士求人JOBSは元保育士が担当!/

「SNSの情報だと怖い」という方は対面での相談が可能!
母子同園の保育園や第2新卒OKなどの非公開求人の取扱いも多数ご用意!
「保育士に向いてないから辞める」は本当に正解?
「私、保育士に向いてないかも…」と感じることは、決して珍しいことではありません。
特に、仕事に慣れないうちは思うようにいかず、落ち込んでしまうこともあるでしょう。
ミスをしたり、子どもとの関わり方に悩んだり、先輩保育士と比べて「自分には向いてない」と感じることもあるかもしれません。
しかし、一度立ち止まって考えてみてほしいのが、「向いてない」と思うその理由です。
保育士の仕事は、多くのスキルが求められますが、最初から完璧にこなせる人なんていません。
経験を積むうちにできることが増え、自信もついてくるものなので、「向いてない」と感じたとしても、それはあくまで一時的なものかもしれません。
「辞めるべきか」と悩む前に、自分にとっての保育士という仕事の意味をもう一度見つめ直してみることが大切です。
保育士にはさまざまなタイプがいる
「保育士に向いてない」と感じてしまう理由のひとつに、「理想の保育士像と自分が違う」と思ってしまうことがあります。
でも、保育士にはさまざまなタイプの人がいて、それぞれの個性を活かして働いているのです。
- いつも明るく元気で、場を盛り上げる先生
- しっかりと子どもを導く厳しめの先生
- 冷静に物事を判断し、的確に動ける先生
- 子どもの話をじっくり聞き、優しく寄り添う先生
- 書類仕事や制作が得意で、サポート役として活躍する先生
大切なのは、「どのような保育士になりたいか」「どのような強みを活かせるか」を考えることです。
他の先生と同じようにできなくても、それが「向いてない」理由にはなりません。
自分の得意なことを活かして働くことで、保育の現場での居場所は必ず見つかるはずです。
子どもが好きという気持ちが大切
どんな保育士にも共通して大切なのは、「子どもが好き」という気持ちです。
もちろん、保育の仕事には大変なことも多く、「子どもが好き」というだけでは乗り越えられない場面もあります。
しかし、それでも続けられる理由の一つに、「子どもと関わることが楽しい」「子どもの成長を見るのが嬉しい」という気持ちがあります。
保育士として、「向いているかどうか」よりも、「この仕事をやりたいかどうか」が重要です。

苦手なことがあっても、「でもやっぱり子どもと関わるのが好きだから頑張りたい」と思えるなら、大きな強みになります。
また、子どもにとって大切なのは、完璧な保育士ではなく、「自分のことを大切に思ってくれる大人」の存在です。
あなたの存在が、子どもたちにとって安心できるものなら、それだけで十分価値があります。
「向いていなかも」と思ったときこそ、なぜ保育士を目指したのかを振り返ってみましょう。
その気持ちを忘れずにいれば、きっとあなたらしい保育士像が見つかるはずです。
合わせて読みたい、保育士に向いていなくて辞めたいと悩む方へ
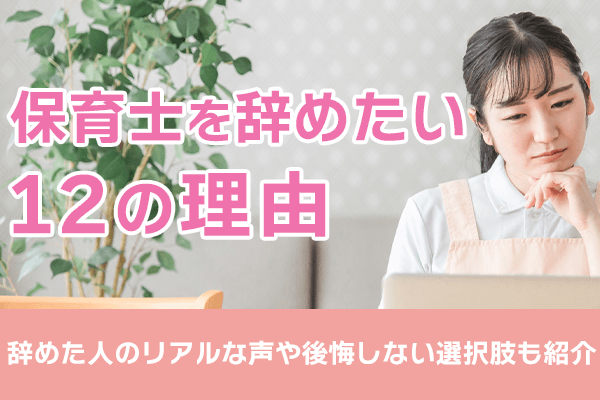
保育士に向いてないと思う人の特徴
保育士に向いてないと感じる理由は人それぞれですが、実際に現場で働いていると、いくつかの共通する特徴が見えてきます。
向いてないと感じるからといって、必ずしも辞めるべきとは限りません。
苦手な部分を理解し、改善できる点がないかを考えることで、無理なく続ける道も見えてきます。
ここでは、保育士に向いてないと感じやすい人の特徴を紹介します。
保護者とのコミュニケーションが苦手
保育士の仕事は、子どもと関わることだけではなく、保護者との連携も大切な役割の一つです。
保護者対応が苦手な場合、以下のような悩みを抱えがちです。
- 保護者との会話がぎこちなく、何を話せばいいかわからない
- クレームや相談への対応が怖く、うまく言葉が出てこない
- 保護者と距離を縮めるのが苦手で、信頼関係が築けない
保護者との関係は、慣れや経験で改善できる部分も多いです。
まずは挨拶を意識し、少しずつ会話を増やしてみましょう。
信頼関係を築くことで、保育の仕事もしやすくなります。
職場環境と人間関係が合っていない
保育士の仕事が向いているかどうかは、職場の環境や人間関係によっても大きく左右されます。
- 上司や同僚との関係がギスギスしていて、職場にいるのがストレス
- 保育園の教育方針や保育のやり方が自分の考えと合わない
- 人間関係のトラブルが多く、毎日気を遣いすぎて疲れてしまう
職場を変えることで、働きやすくなることもあります。
転職を視野に入れることで、より良い働き方を見つけられる可能性があります。
自分に合った職場を見つけることで、より充実した働き方ができるようになるでしょう。
業務量が多く体力や健康面が続かない
保育士の仕事は長時間立ちっぱなしや、子どもを抱っこすることが多いため、体力的に厳しく感じることがあります。
- 体力に自信がなく、日々の業務についていけない
- 忙しすぎて、休憩が取れず、疲労が蓄積している
- 慢性的な腰痛や体の不調を抱えている
体力面で続けるのが難しい場合は、負担の少ない働き方を検討するのも一つの方法です。
パート勤務や企業内保育など、比較的負担の少ない職場もあります。
また、日常的にストレッチや軽い運動を取り入れることで、少しずつ体力をつけていくのもおすすめです。
子どもとのコミュニケーションが上手くできない
子どもが好きでも、実際に関わる中で「どう接していいかわからない」と感じることもあります。
- 子どもの気持ちを理解するのが難しく、うまく関われない
- どう対応すればいいのか迷い、戸惑ってしまうことが多い
- 叱るべき場面で適切な対応ができず、不安になる
子どもとの関わり方は、経験を積むことで自然と身についてくるものです。
焦らず、周りの先生のやり方を見ながら、自分なりの接し方を見つけることが大切です。
また、子どもとの距離感を少しずつ掴むことで、関係性が深まり、自然とコミュニケーションが取りやすくなることもあります。
子どもに対して愛情が薄れてきている
最初は子どもが好きで保育士になったものの、日々の業務の中で気持ちに変化が生じることもあります。
- 仕事に追われるうちに、子どもと関わる楽しさを感じなくなった
- イライラすることが増え、子どもに対して冷たくなってしまう
- 仕事を義務的にこなすだけになり、やりがいを感じなくなった
こうした気持ちが続く場合は、一度休みを取る、保育士以外の選択肢を考えるなど、自分の気持ちと向き合うことが必要かもしれません。
気持ちがリフレッシュされると、また前向きに子どもと関わることができる場合もあります。
汚れることに抵抗感がある
保育士の仕事では、子どもと一緒に遊ぶ中で汚れることが避けられません。
- 給食やおむつ替えで手が汚れるのが苦手
- 泥遊びや絵の具遊びなどに抵抗がある
- 子どもが鼻水やよだれをつけてくるのが気になる
汚れることが苦手でも、慣れることで気にならなくなる人もいます。
ただ、どうしても抵抗がある場合は、保育士以外の子どもと関わる仕事(幼児教育関連・事務職など)を考えるのも一つの手です。
潔癖症などの理由で強い抵抗がある場合は、自分にとって無理のない職場環境を選ぶことが大切です。
保育士に向いてない時に感じる自信には2種類ある
「自信がないから保育士に向いてないのかも…」と感じることは、保育士として働く上で誰もが一度は経験する悩みです。
しかし、自信があるかどうかだけで保育士の適性を判断するのはやめましょう。
実は、自信には大きく分けて「安定型自信」と「防御型自信」の2種類があり、それぞれ性質が異なります。
- 安定型自信
経験や知識を積み重ねることで生まれる健全な自信で、保育士が持つべきもの - 防御型自信
自分を守るために作られた見せかけの自信で、場合によっては保育の現場で危険を伴う
ここでは、この2つの自信の違いについて詳しく解説していきます。
参考:J-Stage│自己肯定感を育むための 3 領域からのアプローチ
安定型自信とは保育士が持つべき健全な自信
安定型自信とは、経験や学びを積み重ねることで生まれる、根拠のある自信のことです。
安定型自信を持つ保育士の特徴は以下の通りです。
- わからないことは素直に質問できる
- 失敗を学びに変えられる
- 他の保育士の意見を柔軟に受け入れられる
- 子どもや保護者に寄り添い、適切な対応ができる
安定型自信を持つ保育士は、完璧を求めすぎず、自分の得意・不得意を理解しながら成長することができます。
些細なことや、積み重ねで自信が育まれていきます。
- 最初はうまくいかなかった子どもへの声かけが、経験を重ねるうちに自然とできるようになった
- 保護者とのやり取りがスムーズになった
安定型自信は「できないことがあっても大丈夫、学びながら成長できる」という前向きな姿勢が基盤にあります。
こうした考え方ができれば、壁にぶつかっても乗り越える力が身につくでしょう。
体験談:保育士Aさんの話
Aさんはピアノが苦手でしたが、絵本の読み聞かせが得意でした。
最初は「ピアノが弾けない自分は保育士に向いてないのでは…」と落ち込むこともありました。
しかし、読み聞かせの時間になると、子どもたちが目を輝かせ、物語に引き込まれる姿を見て、「自分の得意なことで子どもたちを楽しませることができる」と実感しました。
Aさんは、「完璧でなくても、自分らしい保育ができる」と自信を持てるようになり、ピアノの苦手さも受け入れながら、自然体で子どもたちと向き合えるようになったのです。
防御型自信とは持っていると危険な見せかけの自信
防御型自信とは、「自分のやり方が正しい」「自分は問題ない」と思い込み、学ぶことをやめてしまう自信のことです。
一見、強い自信に見えますが、実際は成長を妨げる原因になりやすいです。
また、防御型自信を持つ保育士の特徴は以下の通りです。
- 他の保育士のアドバイスを受け入れない
- 失敗を認めず、言い訳や責任転嫁をする
- 子どもや保護者に対して一方的な対応をする
- 改善点を指摘されると過剰に防衛的になる
このタイプの自信を持ち続けると、周囲との関係が悪化し、子どもへの関わり方も偏ってしまうことがあります。
- 私は、皆からの信頼が厚いから大丈夫
- 子どもが成長するためには、絶対コレをした方が良い
保育士として成長するためには、「まだまだ学べることがある」と謙虚な姿勢を持つことが大切です。
大切なのは、完璧な自信ではなく、成長し続ける意識を持つことなのです。
体験談:保育士Bさんの話
B先生は、いつも「大丈夫、私に任せて!」と自信に満ちた態度で、子どもたちや保護者から厚い信頼を寄せられていました。
しかし、運動会のリハーサル中、子どもたちを引率している際に油断し、子どもが転倒してケガをしてしまいます。
Bさんは「私は大丈夫」という過信が慎重さを欠く要因となり、大きなミスへと繋がってしまったのです。
保育士に向いてないと感じたときの対処法

保育士に向いてないと感じる瞬間は誰にでもあります。
しかし、すぐに辞めるという選択をする前に、その気持ちの原因を整理し、解決策を考えることが大切です。
環境の変化やスキルの向上によって、状況が改善することもあります。
ここでは、保育士に向いてないと感じたときに試したい対処法を紹介します。
- 向いてない感じる理由を整理する
- 職場環境を見直す
- 苦手を克服するためのスキルを磨く
- 同僚や先輩に相談する
- 休息を取ってリフレッシュする
向いてない感じる理由を整理する
保育士に向いてないと感じる理由は、人によって異なります。
仕事が思うように進まないからなのか、職場の雰囲気に馴染めないからなのか、あるいは子どもとの関わり方に自信が持てないからなのか、一度自分の気持ちを整理してみましょう。
感情だけで「向いてない」と決めつけるのではなく、具体的にどのような場面でそう感じるのかを考えることが大切です。
原因がはっきりすると、対策もしやすくなります。
「何ができないのか」ではなく、「どうすれば改善できるのか」という視点を持つことで、気持ちが前向きになることもあるでしょう。
職場環境を見直す
保育士に向いてないと感じる原因が、仕事内容ではなく職場環境にあることも少なくありません。
方針や教育スタイルが自分と合わなかったり、人間関係がうまくいかないと、仕事そのものが嫌になってしまうこともあります。
また、仕事量が多く、休憩が十分に取れない環境では、精神的にも体力的にも負担が大きくなります。
もし環境が合わないと感じるのであれば、転職を視野に入れるのも一つの方法です。
保育士の仕事は、園によって雰囲気や働き方が大きく異なるため、自分に合った職場を探すことで、同じ仕事でも負担が軽減されることがあります。
苦手を克服するためのスキルを磨く
「向いてない」と感じるのは、単に経験やスキルが不足しているだけかもしれません。
子どもへの接し方や保護者対応、業務の進め方に自信がない場合は、学ぶことで解決できることも多いです。
- コミュニケーション力を高める
保護者対応の練習をする(ロールプレイングを行い、相談やクレーム対応の受け答えを実践) - 保育スキルを向上させる
保育書や絵本の知識を読んだり、SNSや研修で最新の保育情報を取り入れる - 指導力・リーダーシップを強化する
行事の準備や制作活動の進行役を担当し、小さなリーダー経験を積む
苦手なことをそのままにして「向いてない」と思い込むのではなく、少しずつ克服する努力をすることで、自然と自信がついてくるでしょう。
同僚や先輩に相談する
一人で悩み続けていると、どんどんマイナス思考になり、「もう無理かもしれない」と追い詰められてしまうため、同僚や先輩に相談してみるのも良い方法です。
同じ職場で働いている人なら、自分と似たような経験をしている可能性も高く、共感してもらえることが多いです。
自分では気づかなかった考え方や工夫を教えてもらうことで、「もう少し頑張ってみよう」と前向きな気持ちになることもあるでしょう。
仕事の悩みは一人で抱え込まず、周囲の力を借りることで、気持ちが楽になることもあります。
休息を取ってリフレッシュする
「向いてない」と感じるときは、心身ともに疲れていることが多いものです。
忙しい日々が続くと、余裕がなくなり、小さなミスやトラブルが重なることで、自信を失ってしまうこともあります。
そんなときは、思い切って休息を取り、リフレッシュすることが大切です。
- 身体を動かしてリフレッシュ
軽いストレッチやウォーキング、ヨガ、ピラティスなど - 趣味を楽しんで気分転換
カフェやアート、音楽、映画見るなど - 友人と食事したり遊んだりする
同僚や仲のいい人と気軽におしゃべりする
仕事のことを忘れて趣味の時間を楽しんだり、友人と会って気分転換をしたりするだけでも、気持ちが軽くなることがあります。
また、可能であれば有給休暇を取って、少し仕事から離れる時間を作るのも良いでしょう。
心に余裕が生まれることで、もう一度前向きに保育の仕事に取り組めるようになるかもしれません。
保育士に向いてないと感じたときの転職先の選び方
「保育士に向いてないかも」と思ったとき、今の職場が合わないだけなのか、保育の仕事そのものに違和感を感じるのかを整理してみることが大切です。
すぐに辞めるのではなく、自分に合った職場を探すことで、無理なく働き続けられることもあります。
同じ保育士の仕事でも、園の規模や方針が変わるだけで負担が軽減されることもあるので、まずは「どんな環境なら続けられるのか?」を考えてみましょう。
ここでは、転職先を選ぶ際のポイントを紹介します。
- 価値観やライフスタイルに合った職場を選ぶ
- 定員数が少ない施設を選ぶ
- 保育士資格を活かせる職場を視野に入れる
価値観やライフスタイルに合った職場を選ぶ
「向いてない」と感じる背景には、職場の方針や働き方が自分の考えと合っていないことが影響していることがあります。
忙しすぎてプライベートの時間がほとんど取れなかったり、園の教育方針に違和感を覚えたりすると、「私、この仕事合ってないのかも…」と感じやすくなります。
でも、保育士としての働き方は一つではないため以下の点を確認して職場を探しましょう。
- 勤務時間・働き方を重視する
残業が少ない職場、シフトの融通がきく職場、有給休暇の取得率が高い職場 - 給与・ボーナス・福利厚生を確認する
基本給が高い、住宅手当などの福利厚生が充実している園 - 職場の雰囲気・人間関係を大切にする
離職率が低く、園長や先輩が相談しやすい環境の園 - ライフスタイルに合った環境を選ぶ
通勤時間が短い、シングルマザー・共働き世帯でも働きやすい環境の園
ワークライフバランスを大切にしたいなら、土日休みや残業の少ない職場を選ぶことで負担を減らすことができます。
また、子どもとゆったり関わりたいなら、自由保育を実践している園を選ぶのも一つの方法です。
今の職場が合わなかった理由を振り返り、「どんな環境ならストレスを感じずに働けるのか?」を考えながら転職先を選んでみましょう。
定員数が少ない施設を選ぶ
子ども一人ひとりと向き合いたいのに、大人数の保育園で毎日バタバタしてしまい、気持ちに余裕が持てない。
そんな経験をしていると、「私、保育士に向いてないかも」と感じてしまうことがあります。
子どもとじっくり関わるためには、以下のような少人数制の施設を選ぶと良いでしょう。
| 施設の種類 | 特徴 | 対象年齢 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 小規模保育園 | ・市区町村の認可を受けた少人数制の保育施設。 ・アットホームな雰囲気が特徴。 | 0~2歳 | 6~19名 |
| 企業内保育所 (事業所内保育所) | ・企業が従業員のために運営する園。 ・地域の子どもも受け入れ可能。 | 0~2歳 | 10~30名程度 |
| 病院内保育 (小規模) | ・体調不良の子どもを一時的に預かる施設。 ・看護師や保育士が常駐。 | 0~5歳 | 30名以下 |
| 家庭的保育事業 (保育ママ) | ・保育士や保育ママが自宅や小規模施設で保育を行う。 ・家庭に近い環境。 | 0~2歳 | 1~5名以下 |
大規模な園での集団保育が合わなかった場合でも、少人数制の施設なら「やっぱり子どもと関わる仕事が好きだな」と思えるかもしれません。
転職を考えるときは、「どんな環境なら保育士として働けるか?」を意識しながら探してみましょう。
保育士資格を活かせる職場を視野に入れる
「やっぱり保育の現場が辛い…」と感じたとき、保育士の仕事そのものを辞めることを考えるかもしれません。
保育士の経験を活かして働ける仕事は意外と多く、現場を離れたとしても、子どもに関わる仕事を続けることは十分可能です。
- 児童発達支援施設
- 放課後等デイサービス
- ベビーシッター
- 託児所スタッフ
また、保育教材の開発や、保育士養成校の講師など、直接子どもと関わらない仕事も選択肢の一つです。
「保育士に向いてない」と思ったとしても、それは今の職場が合っていないだけかもしれません。
資格を活かせる働き方はたくさんあるので、「どんな仕事なら続けられそうか?」を視野を広げながら考えてみましょう。
保育士に向いてないと感じる人のよくある質問
「保育士は向いてないかも」と同じ悩みを抱える人は多く、よくある質問を知ることで解決策が見えてくることもあります。
ここでは、保育士としての悩みや転職に関する疑問について回答していきます。
子どもにイライラしてしまうときはどうしたら良い?
イライラするのは、疲れやストレスが溜まっているサインかもしれません。
まずは深呼吸をして気持ちを落ち着けることが大切です。
余裕がないと感じたら、周りの先生に相談したり、こまめにリフレッシュする時間を作るのも有効です。
保育士を辞めた人はどんな仕事をしているの?
保育士を辞めた後は、児童発達支援施設や学童指導員、ベビーシッターなど、資格を活かした仕事に就く人が多いです。
また、保育関連の事務職や保育教材の開発、企業の託児所スタッフなど、現場以外で活躍するケースもあります。
保育士が辞めたくなる理由は何ですか?
多くの人が「人間関係」「仕事量の多さ」「給与の低さ」などを理由に辞める傾向があります。
また、保護者対応のストレスや、体力的な負担が大きいことも、離職を考える要因の一つです。
ADHDは保育士に向いてない?
そんなことはありません。
ADHDの特性によっては、スケジュール管理や細かい作業に苦手意識を持つことがありますが、子どもと遊ぶことが得意だったり、柔軟な対応ができたりする長所もあります。
自分に合った働き方を見つけることで、保育士として活躍することも可能です。
まとめ
保育士に向いてないと感じることがあっても、環境や働き方を見直すことで負担を減らせることもあります。
悩んだときは、一人で抱え込まずに周りの人に相談することも大切です。
自分に合った働き方を見つけながら、無理のないキャリアを築いていきましょう。



